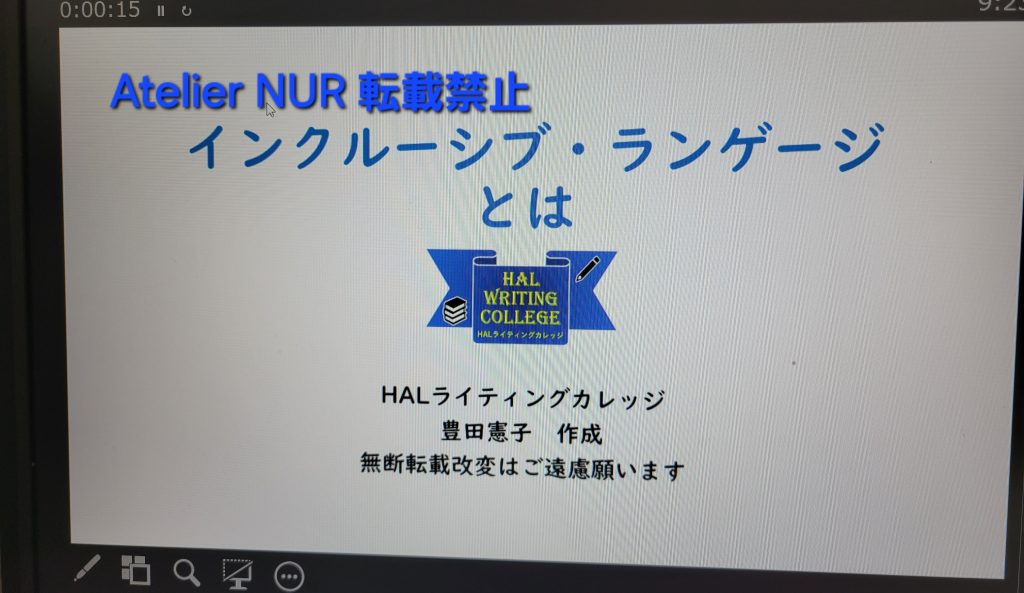今回は当カレッジが実施している企業出張講義についてどんな内容やどんなことに留意しているのか、ちょっとご紹介します。こちらは先週実施した企業出張講義についてです。
いつも参加者の意見が活発で、こちらにも刺激になります。今回のテーマは誰かの発言を訳すときのポイントや注意点。スタイルガイド的なダッシュや三点リーダーの処理や、会話が続くときに「~が言った」調が続くのを避ける方法などご紹介。 そして、ここからが重要なテーマ。内容に誤解を与える文言やミスリードがないかの確認です。新聞やネットに見られる「誰かの発言は切り取られている懸念が大」なので、できれば目の前の文章だけでなく他にも同じ発言資料がないか探して、内容に齟齬がないかを確認するほうが良いとお話ししました。
実際、先日の教皇レオ14世のスピーチを紹介した日本語記事に違和感ある訳を発見。原文を見たらdevelopmentsとあります。日本語記事では「発展」と訳されていたのですが、その訳では論旨がうまく流れません。そこで、英文元発言を複数紙で探したら上記だったというわけです。
さあ、皆さまだったらどうしますか? 裏取りが大事です。その結果、新教皇が前教皇と考えを同じく前教皇の方針を受け継いだことが判明しました。さらに同業者さんからオリジナルイタリア語でも「発展ではなく状況という意味だった」とのご教示をいただいたのです。
こうやって見ると、ひとつの単語だけ見るのはとても怖いことです。問題の日本語記事ではいくつか訳抜けしていることも判明し、無理してつないでいるように見えました。本人が発言した内容と逆の発言に誤解されるのはまずいですね。酷い場合には名誉棄損になることもあります。切り取りや勝手読みには十分気をつけようという話になりました。
こういう上記事例は翻訳だけでなく日本語においてすらあります。私が何年か前に受けた翻訳学校広報インタビューで、ライターさんの書き起こしまとめを確認したら、残念ながら肝心なキーワードがいくつか削られていたことがありました。「本当は削られたところが大事なのよね……」。そのときのライターさんの状況を類推すると、削られた前後でつじつまが合わず(どこか聞き漏らしていたのかもしれません)切り取り貼り付けにしたので部分的に落ちたところがあったのでしょう。
百歩譲って個人的なことなら妥協することもありますが、学校の広報仕事なので、言葉には気をつけつつもキーワードを入れて修正していただきました。このようなこともあるので、要約や議事録作成時にはご本人や他の人にも内容をチェックしてもらって内容に齟齬がないかどうか慎重に進めることが大事と、今回講義でも全員で確認しました。実在する人がからんでいるだけに単なる誤訳だったですまない場合もあるので気をつけたいところです。
最近はコストカットの面から要約や議事録を生成AI頼みにする企業もあるとお聞きしますが、生成AIには誤字脱字までならともかく、誤訳の判断や正誤の判断ができません。勝手に内容を足すハルシネーションという行為まであります。ご自分では効率よくと思ったことがとんでもない誤解を生み、お得意様との間や社内関係で不和をもたらすこともあります。慎重にお考えになることをお勧めいたします。
当カレッジでは上記のように、批判的論理的思考を基盤にして人間にしかできない内容の講義やカウンセリングを行っております。社内コミュニケーションの円滑化や翻訳の枠を超えた内容にもお応えしております。時間回数などはオリジナルでお引き受けしております。ご興味があればいつでもお問い合わせくださいませ。お待ち申し上げております。(写真は先月実施した「インクルーシブランゲージ」についての講義です)